 |
 五月広場(Plaza de Mayo) 五月広場(Plaza de Mayo)
ブエノスアイレスの中心広場。その名は、独立運動が始まるきっかけとなった「五月革命」(1810年5月25日)に由来する。大統領府、カビルド、大聖堂などの史的重要建築物に囲まれ、しばしば抗議デモの中心部ともなる。大統領府正面にある、旗を持ち馬にまたがった勇士の像は、10ペソ札の肖像でも親しまれているマヌエル・ベルグラーノ将軍で、アルゼンチンの国旗は彼によって創られた。広場中央には「五月のピラミッド(Pirámide de Mayo)」と呼ばれる、五月革命1周年を記念して1811年に建てられた白い塔があり、バラ色の大統領府に重なって涼しげなコントラストを生んでいる。広場の西側からは五月通りが大統領府と国会議事堂間を結んでおり、同広場から通りを進んでいくと、まっすぐ続く道の向こうに悠々たる国会議事堂が見えてくる。 |
 |
 大統領府 (Casa de Gobierno) 大統領府 (Casa de Gobierno)
別名「カサ・ロサーダ(Casa Rosada-バラ色の家の意)」。1862年から現在まで歴代大統領の行政の場として役割を果たしてきた。建物がバラ色に塗られた理由は、サルミエント大統領が、国のまとまりの象徴として、当時の2大政党、連邦主義派(Federales)と中央集権主義派(Unitarios)のイメージカラー(それぞれ赤と白)を合わせたバラ色を選んだことによるという。しかし当時は非常に塗料の種類が少なかった時代。苦心の末、石灰と牛の獣脂、血を混ぜて紅茶色ともつかぬバラ色を作り出した。その後塗りかえられて現在の色はオリジナルではないが、青いブエノスアイレスの空に映えて立つバラ色の大統領府は独特の華やかさを湛えている。 |

|
 カビルド (Cabildo) カビルド (Cabildo)
市内で最も歴史ある建物の一つ。コロニアル調のシルエットが美しい建物である。ブエノスアイレスが市として機能するようになった1580年代から1800年代まで市議会として、数々の重要決定がここでなされた。1810年5月25日、五月革命の舞台となったのも、ここである。もとは左右それぞれに五つのアーチを持ち、五月広場の一画全てを占めるほど大きな建物だったが、1880年代、五月通りをつくる際に一部が取り壊され、その後も縮小されて現在の大きさになった。現在は博物館として植民地時代の家具、調度品等が展示されている。 |

|
 大聖堂 (Catedral Metropolitana) 大聖堂 (Catedral Metropolitana)
1593年に原型となる聖堂が造られ、幾度にも渡る立て直しの末、現在の建物が1827年に完成された。同大聖堂には、アルゼンチンを独立へと導いたサン・マルティン将軍の眠る霊廟が安置されており、多くの観光客がそれをひと目見るため訪れる。
大聖堂入り口に毅然と並ぶ12本の円柱はイエス・キリストの12使徒を表現し、その上壁にほどこされた彫刻は、エジプトの総督となったヨセフとその父ヤコブの対面という旧約聖書の一場面を表している。また、入り口向かって右側の壁に掲げられている「永遠の炎」はサン・マルティン将軍を記念して燃え続けているものである。中に入ると、ひんやりと静寂な空気が身を包み、広い会堂が天窓から差しこむ淡い光の中おごそかに浮かび上がる。主祭壇からは黄金色に輝く荘厳な「我らの聖母ブエノスアイレス」が祈りに来る人たちを優しく見下ろしている。 |

|
 国会議事堂広場 (Plaza de los Dos Congresos) 国会議事堂広場 (Plaza de los Dos Congresos)
国会議事堂前に広がる大広場。国会議事堂の正面にあるモニュメントは、「二つの国会の記念碑(Monumento a los Dos Congresos)」と呼ばれ、奴隷制を廃止した1813年の憲法制定議会と、スペインからの独立を宣言した1816年のトゥクマン国会の2つを記念したもの。また広場の反対側には、世界に6つしかないと言われるロダンの彫刻「考える人」のレプリカがある。この「考える人」のそばにある一本石の碑は、"ゼロキロメートル地点"を示しており、ブエノスアイレスから始まる国道はこの地点から距離を数え始める。 |

|
 国会議事堂 (Congreso Nacional) 国会議事堂 (Congreso Nacional)
アルゼンチンの立法最高機関。8年もの年月を経て建築され、1906年にフィゲロア・アルコルタ大統領によって落成された。そのグレコ・ローマン様式は民主主義の恒久価値を表し、建物中央上部の銅像は国家権力を象徴する。ドームの緑色は建築当初の予定にはなかったが、青銅製であるため時が経つにつれて現在の色になっていったという。内部は、大理石や銅の彫刻、赤い絨毯、絹のカーテンに彩られた絢爛な造りになっており、南に上院、北に下院がある。中でも素晴らしいのが、ドームのちょうど真下に位置する中央ホール「青の広間(Salón Azul)」と、「足跡の間(Salón de los Pasos Perdidos)」。青の広間にある重さ2トンのシャンデリアはガラスと銅でできており、アルゼンチンの各州を表現している。また、同建物内には図書館もあり、一般の人も利用可能となっている。この図書館は約2百万冊もの書物を有し、アルゼンチンで最も在庫図書数のおおい図書館の一つである。 |

|
 7月9日通り (Avenida 9 de julio) 7月9日通り (Avenida 9 de julio)
大統領府と国会議事堂を結ぶ五月通りと交差して市の中心を走る大通り。南北4km、最大幅約140m、16車線の規模を誇る。アルゼンチン人曰く、世界で一番幅の広い道路であり、1回の青信号で渡り切るのは難しい。その名はアルゼンチンが独立を果たした1816年7月9日に由来する。同通りができる以前、この一帯にはフランス様式の家々が立ち並んでいたが、1936年、この通りを作るためそれらは全て取り壊された。唯一フランス大使館のみが取り壊しを免れ、7月9日通りがリベルタドール通りに合流する部分に今でも美しくそびえ立っている。
 オベリスク (Obelisco) オベリスク (Obelisco)
7月9日通りとコリエンテス通りの交わる部分に位置。1936年にブエノスアイレス創設400周年を記念して建てられた、ブエノスアイレスの視覚的シンボルである。高さ68m、底辺7mX7m。オベリスクが立つ広場は共和国広場(Plaza de la República)といい、しばしば市民の集会の場となる。 |
 |
 コロン劇場 (Teatro Colón) コロン劇場 (Teatro Colón)
世界でもっとも音響効果の良い劇場の一つといわれ、ヨーロッパがシーズンオフとなる5~11月には世界的に有名なオーケストラや音楽家が訪れ、公演を行う。また、コロン劇場自体も国立オーケストラや国立バレエ団、舞台装置や衣装を作る工房などを有しており、まさにブエノスアイレスの高い文化レベルの象徴的存在である。
コロン劇場は当初、五月広場の一角に位置していたが、1880年代の移民増加を機に、現在の建物が新設された。建設は約20年の歳月を経て1907年に完成。1908年5月25日、ヴェルディのオペラ『アイーダ』でこけら落としとなって以来、ルシアーノ・パバロッチ、マリア・カラスなど数々の有名オペラ歌手、有名オーケストラがその舞台を踏んでいる。
正面玄関から入ると白大理石のモザイクがほどこされた床、紅大理石や黄大理石の荘厳な手すりや柱、色鮮やかな天井のステンドグラスと、玄関ホールの美しさに息をのむ。大ホールは、真紅の垂れ幕に縁取られた舞台を正面に、蹄型に7階建ての観客席が広がり、定員は2450名、立ち見を合わせると約3000名を収容できるようになっている。天井ドームにはラウル・ソルディによって描かれた歌い手や役者、踊り子、楽器を表現した壁画があり、その中央には直径7mになる巨大なシャンデリアが輝く。
チケットは公演の数日前よりコロン劇場にて直接販売。劇場見学(ガイド付き、西または英語)はシーズンに関係なく年中可能である。
|

|
 レコレータ墓地 (Cementerio de Recoleta) レコレータ墓地 (Cementerio de Recoleta)
ブエノスアイレスでも有数の高級住宅地にあるこの墓地には、アルゼンチン史上著名な権力者や大富豪一族が眠っている。上品に立ち並ぶ石造りの、まるでチャペルのようなお墓や彫刻の数々は、建築学また芸術的観点から見ても価値が高いといわれる。この墓地の一角に、「エビータ」の愛称で知られているエバ・ペロンは葬られており、現在でも彼女を慕う人々によって絶えることなく花が捧げられている。 |

|
 サン・マルティン広場 (Plaza Libertador General San Martín) サン・マルティン広場 (Plaza Libertador General San Martín)
樹木が涼しげな影を落とす緑豊かな美しい広場である。アルゼンチンの独立運動を指揮し、チリ、ペルーまでも独立へと導いた「祖国の父」、サン・マルティン将軍の像がある。また、広場のリベルタドール通りに面する所にはマルビーナス戦争(フォークランド紛争)で亡くなった兵士たちの名を25枚の黒大理石板に刻んだ戦没者祈念碑がある。
同広場の一角からは1kmに渡ってフロリダ通りという歩行者天国のブティック街がのびており、良質な革製品や、別名「インカのバラ」と呼ばれるピンク色の鉱石「ロードクロサイト(Rodocrosita)」など、アルゼンチン特産のいろいろなお土産が購入できる。
|

|
 空軍広場/イギリス人広場 (Plaza de la Fuerza Aérea / Plaza de los Ingleses) 空軍広場/イギリス人広場 (Plaza de la Fuerza Aérea / Plaza de los Ingleses)
イギリス風の時計台で知られるこの広場は、ガイドブック等によるとマルビーナス戦争以来改名され、「空軍広場」となったらしいが、ブエノスアイレスの人々の間にはまだ「イギリス人広場」として定着しているようである。時計台は1916年に、独立100周年を記念してイギリス系移民の人々によってブエノスアイレス市に寄贈された。塔の高さは59m、時計の直径は4,4mにもなり、重さ7トンの鐘が時をつげる。 |

|
 プエルト・マデーロ (Puerto Madero) プエルト・マデーロ (Puerto Madero)
もとはラプラタ川沿いに並ぶ煉瓦造りの倉庫群だったが、近年外観の趣をそのままに内部を改装し、おしゃれなオフィスやカフェテリア、高級レストラン街となった。建物に沿って続く2kmほどのきれいな遊歩道は散歩するだけでも気持ち良く、各レストランもそのシックな雰囲気や涼しげな景観で人気を集めている。 |
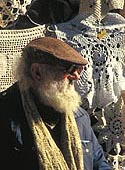
|
 サン・テルモ地区 (San Telmo) サン・テルモ地区 (San Telmo)
ブエノスアイレスでもっとも歴史ある地区の一つ。石畳の通りや古めかしい家々が一昔前のブエノスアイレスの人々の生活を彷彿させる。
同地区は18世紀当時、市場のあった五月広場からリアチュエロ川沿いの倉庫へと向かう商人たちの休憩の場として栄えた。その後、19世紀初めには裕福な人々が家を並べるようになり、高級住宅区となった。しかし、1870年代、黄熱病の大流行があり、多くの住民はブエノスアイレスの北の地域へ逃げ移った。現在は、サン・テルモ地区が高級住宅区であった時代の調度品や家具をおく骨董屋が軒を並べ、毎週日曜日にはドレーゴ広場(Plaza Dorrego)を中心に骨董品や古美術品の露天市が華やかに行われる。またサン・テルモ地区は有名なタンゴ・ショーの店が多いことでも知られており、ブエノスアイレスを訪れるならば必ず一回は立ち寄ることになりそうである。 |

|
 ボカ地区 (La Boca) ボカ地区 (La Boca)
一説にてタンゴ発祥の地といわれるこの地区は、市中心部から南に位置する旧港町である。一角には、タンゴ不朽の名作「カミニート(Caminito-小路の意)」に関連づけて画家キンケラ・マルティンが創作したという、カラフルな家々にはさまれた100mほどの小路があり、観光名所となっている。キンケラ・マルティンはボカ地区に育ち、ボカ港や労働者の生活の様子を描き続けた。力強い筆致、鮮やかで大胆な色遣いが非常に特徴的な画家である。このキンケラ・マルティンの影響もあり、毎週週末になると、小路「カミニート」周辺には蚤の市がたち、地域の画家たちがそれぞれの作品を売りに出す。キンケラ・マルティン美術館で様々な絵画を見ることが出来る。
また同地区には、ブエノスアイレスで圧倒的な人気を誇るサッカーチームの一つ、ボカ・ジュニアーズのホームグランドがあり、その競技場はこぢんまりとした規模から愛称「ボンボネラ(La
Bombonera-ボンボンの小箱の意)」と呼ばれる。1986年のサッカー・ワールドカップでアルゼンチンを優勝に導いたディエゴ・マラドーナも同チームの出身である。
|

|
 2月3日公園 (Parque 3 de Febrero) 2月3日公園 (Parque 3 de Febrero)
通称「パレルモ公園」で知られるこの公園は、総面積4平方km、敷地内に動物園、林、池、ゴルフ場、プラネタリウムなどを有し、ジョギングや散歩に来る人々、ピクニックに来る親子連れなどでいつもにぎわっている。週末になると爽やかな空気の中、青空エアロビクスやヨガ教室など様々な催し物が行われる。
また、同公園の一部にある「日本庭園(Jardín Japonés)」は、1967年の皇太子同妃両殿下(現在の天皇皇后両陛下)の亜ご訪問に際し,日系社会が記念事業として造成を決めた和の庭園。在亜日本人会創立60周年の記念事業で改修され、きれいになった。一般のアルゼンチン人にも広く親しまれており、週末は多くの家族連れで賑わう。
|
 コスタネーラ・ノルテ (Costanera Norte) コスタネーラ・ノルテ (Costanera Norte)
ブエノスアイレス市の北東側をラプラタ川に沿って走るこの通りには、数件のパリージャ・レストラン(炭焼肉料理屋)があり、広い川を眺めながら(天気の良い日には対岸のウルグアイも見える)アルゼンチン名物の炭焼肉をワインとともに楽しむことができる。
|